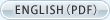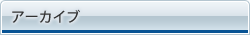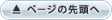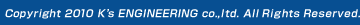第19話 中小企業(300人以下)の組織の再構築
2013年2月26日
第5話でもお話しましたが「ムダ取り」とは、ある狭い四次元空間を切り取り、ある目的に沿った角度から
より細かく視ることにより、そ こに潜む目的に合致しないモノ、方法、
行動を正にピンセントで摘まむ様に、関係者と一緒になって拾い上げる活動である。
企業にとっての「ある目的に沿った角度」とは利益を恒久的に創出し続けることであり、
県庁にとっての「目的」とはバランスの取れた県財政のもとで県民サービスの向上であった。
岩手県の場合、まずはバランスの取れた県財政再構築が第1ステップの目標となった。
その活動内容は拙著を参照してください。(「トヨタ式ホワイトカラー革新」-日経出版)
このとき、担当課長に私は聞いた、
「この部の人員の算出の根拠は何かありますか?」
「ないです。メーカーはありますか?」
「日本の多くのメーカーは、直接作業員についてはストップウォッチによって標準作業時間を設定して
この時間に来月または来々月の生産数を予測した数値を積算して人数を出しています。
これは大企業、中小企業を問わず、ほとんどのメーカーの直接作業員算出の根拠です。
しかし、スタッフ、間接員についてはナイですネ。」
「間接員については何かないですか?」
「私が聞いたのはアメリカのケースです。アメリカのメーカーはスタッフ、間接員は直接員比で
5%(中小企業で)位の様です。ですから日本と較べてもはるかに少ないのです。」
「何か理由はあるのですか?」
「1つはスタッフ、間接員は自ら稼がない。即ちトップとしてはコストという考え方です。
もう1つはスタッフ、間接員が必要なときは知恵を借りる時が多いですから、そのときはコンサルタントを使う
という考え方です。また、アメリカではスタッフとクラークを厳密に区別しています。
クラークは一般の事務員で時間給が多いですネ。」
「本庁の現5,000人のスタッフを本当に考えるスタッフとクラークに分けるとすれば、
本当のスタッフは何%位ですか?」
の質問に私は「20%~30%位ですかネ」と答えたことがある。
企業(特に中小企業)の人員の算出の根拠は何だろうか?
この議論は130年位前アメリカで既に起こっていた。工場経営を例にとると、当時アメリカの工場は1人のボスの下で
数人の秘書の他は数人のホワマン(職長)に引率された数十人~数百人のワーカーで構成されていた。
A.W.テーラーはこの様な工場組織に対し、より効率のよい(利益の上がる)組織の改革を提案した。
これがライン&スタッフ組織の提案である。
スタッフ組織の主なるものは労務、生産計画、調達、標準、検査等であった。
これは極少数の人数で構成され、それぞれが専門化された人々であった。
当時のアメリカは正に産業革命の最中にあり、造ってはすぐ売れる、いわゆる右肩上がりの市場であった。
この頃の人算出はまず市場の動向を見て、直接員を算出する。(前述に近い形で)
次に間接員(スタッフ)は直接員のある比率(私が聞いたのは多くは5%未満)とする。
これが当時のアメリカの数百人未満の工場の実態だった様である。
アメリカの中小企業(300人未満)の工場組織は、私の知る所では、現在でもライン主体組織が中心ではなかろうか。
第2次世界大戦後、日本の中小企業にもこのライン&スタッフ組織が導入された。
幸い、日本も高度成長という右肩上がりの市場が続いた。
しかし、この20年日本の市場は右肩上がりではナイ。そうなると輸出に頼るか、組織の再構築しかナイのではないか。
それほど間接員(ホワイトカラー)の負担が大になっている。
日米同業種比較してみると、日本のメーカーは製造直接原価ではやや優勢であるが、
総原価は負けている場合が多いと聞く。
また、昨今の対中国との関係を見ると、中小企業の輸出はよほどの技術的優位性がない限り、
単独輸出はリスクが大きい。
そうなると組織の再構築が企業存続の第1の決め手であると思う。
組織の再構築を行うのに、その前提として、
①家族主義、平等、博愛、身分保証
②直接員も間接員もナイ、全員が仲間
③マーケットの状況によって時には直接員、時には間接員
④専門職は必要に応じて発生する。 -マーケットの必要に応じて時には技術員、時には営業マン
⑤机はできるだけ一箇所に集中 -大部屋化
この前提に立って、
オンリーワンの因子を積極的に育てる。
・わが社の長所を更に発展させる因子は何か
・これから5年かけて何を長所に成長させるか
を具体的に展開する。
P.F.ドラッカーの言う21世紀型の組織は、正に①~⑤を前提に、オンリーワン因子を積極的に育成する体制を具体化した
ジャズバンド型になると思われる。
特に⑤はトヨタで既に実施されている。
(近藤 哲夫)
第18話 省力化、省人化、少人化
2013年2月13日
省力化、省人化は1970年代から1980年にかけて、日本中に大流行した言葉である。
所がこれが2000年代にかけてお隣の国々で当たり前(?)になっているのには驚いた。
最初、英語でSAVE POWERと聞いた時は電力のエコ節電と勘違いした。
あとで日本語の省力化 ―Mechanization―と聞いて、またビックリ、立派な(?)自動機
を買い入れて、「わが社もようやく近代化しました」とミエを張っていた。
「それで作業者は減らしたのですか?」と質問したら、
「チョコ停(これも日本語で)が多くて作業者はまだ減らしておりません。」との答え。
それでは「電気代と減価償却費分だけコストアップになりますネ。」
「それで困っています。」との返答。
それからはチョコ停減少のためのPM活動(Production Maintenance活動)、即ち
注油、清掃、点検周期、部品交換、日常保全として機械の締付部の増締め等のトレーニング
を実施した。
同時に、いくつかのセンサを設置し、非常の場合、ワーク(加工品)が定位置に停止する様にして、
(即ち機械に知恵を つけて人間の様な動きをさせる)作業者が機械から離れられる様にした。
これが省人化である。
省人化とは、自動機を自働機にすることである。
大野さんは省人化についても
「最初から生産量が増加することを予想して作業員をより多く配置するから、後で人を省くことになる。
最初に少ない人数でやりなさい。」と言った。
事実、1976年3月、マークⅡバン、ワゴンの新車生産の時、大野さんからの1975年の夏頃の指示は
1ヶ月1500台であった。従って最初の人員は1500台体制の人員であった。
3ヶ月後に8400台/月になった。この時ほど、生産設備の補強に、工場の技術員や生産技術部メンバーが
ほとんど昼夜を問わず立ち会ったことはない。
少人化は工場と生産技術のチームワークによって達成したと言っても戯言ではない。
少人化はトヨタでは省人化と同じ発音のために「目のナイ ショージンカ」と呼んだ。
「省力化」「省人化」はどちらかと言えば、機械、設備周りの改善であるが、「少人化」は
機械、設備は勿論、チームワークによる会社全体の改善と言える。
これを私にやらしてくれた大野さんに正に感謝、感謝である。
(近藤 哲夫)